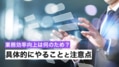テレアポ(アウトバウンド)とは?メリット・デメリット、代替手段についても紹介【2023年最新版】
テレアポとは「テレフォンアポイントメント」の略で、電話でアポイントを取る営業活動を表す言葉です。今回はテレアポの基礎知識に加えて、メリット・デメリット、実施する際の流れやコツ、失敗しないための注意点などを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、基礎知識から実践的な知識までを理解し、適切な運用に役立てられるでしょう。効率的なリード獲得方法も合わせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.テレアポ(アウトバウンド)とは?
- 2.営業活動におけるテレアポ(アウトバウンド)役割
- 3.テレアポ(アウトバウンド)の種類
- 4.テレアポ(アウトバウンド)のメリット
- 5.テレアポ(アウトバウンド)のデメリット
- 6.テレアポ(アウトバウンド)の流れ
- 7.テレアポ(アウトバウンド)のコツ
- 7.1.トークスクリプトの磨き込み
- 7.2.Q&Aの準備
- 7.3.データの蓄積/活用
- 8.テレアポ(アウトバウンド)を行う方法
- 8.1.自社の営業担当(フィールドセールス)で行う
- 8.2.自社のインサイドセールスで行う
- 8.3.営業代行会社に外注する
- 9.テレアポ(アウトバウンド)の注意点
- 9.1.架電リストの重複
- 9.2.架電効率の把握
- 9.3.他アポイント獲得チャネルとの比較
- 10.テレアポ(アウトバウンド)の代替手段にはビジネスマッチング
- 11.まとめ
テレアポ(アウトバウンド)とは?
テレアポは「テレフォンアポイントメント」の略で、言葉の意味が示すとおり、電話でアポイントを取る業務を表します。個人向け、法人向け両方の分野で広く活用されており、数ある営業手法の中でも長い歴史を持っています。
近年ではインターネットの普及や新たなマーケティング手法の確立により、Web広告やSNS運用などさまざまな営業手法が登場していますが、未だにテレアポの地位は揺らいでいません。大きな理由はやはり、電話という手段自体がリアルタイムに顧客と双方向のコミュニケーションが取れる、という点でしょう。
広告やメールなどは顧客へのアプローチ自体は可能なものの、顧客の反応をリアルタイムで分かりやすく確認できませんし、反応に合わせて自由に訴求内容を変えるのも難しいのが現実です。一方テレアポの場合は顧客の反応や温度感に合わせて対応を変えられるため、柔軟なアプローチを実現できます。
営業活動におけるテレアポ(アウトバウンド)役割
商材を問わず、企業が継続的に収益を確保するためには新規顧客獲得が欠かせません。この点において、顧客との意思疎通を能動的に図りやすいテレアポは「見込み客への接点創出」というファーストコンタクトに適しています。
テレアポ(アウトバウンド)の種類
一言でテレアポといっても、具体的な方法はインサイドセールスで行われる「BDR」と「SDR」に分けられます。ここでは、両者の役割や特徴を順に解説しますので、ひととおりチェックしてみましょう。そもそもテレアポは「アポを取る」というのが主な目的であり、テレアポだけですべての目的を達成できるわけではありません。
したがって、BDRとSDRの仕組みを理解した上で、自社の商材や環境に適した手法を選択することが大切です。
BDR
BDR(Business Development Representative)は、顧客に対して自発的にアプローチを行う新規開拓型の営業手法です。対面式の営業手法に例えると飛び込み営業に近く、アプローチしたい企業をリストアップした上でテレアポを実施するスタイルとなります。BDRの特徴は、アプローチの発端がテレアポを実施する企業側にあり、顧客の顕在的なニーズに左右されないという点です。
そのため、実際に電話してやりとりするまでは相手の興味関心の度合いが分かりません。したがって、ゼロから相手の興味関心を引き出し、アポへつなげていく必要があるまで、主導的にアプローチの内容を決定した上で、事前に練った戦略に沿って会話を進めていくのが基本です。
SDR
SDR(Sales Development Representative)は、自発的なBDRとは異なり、反響型に分類される営業手法です。具体的にはまず、資料請求や問い合わせなど顧客から何らかのアクションがあった場合に電話でアプローチを行います。事前に顧客自らアクションを起こしていることから、一定の興味関心を抱いている顧客に対してアプローチできるのが大きな特徴です。
ただし、顧客がアクションを起こした直後の興味関心が高い状態でアプローチすることが大切であり、タイミングを逸する意欲が低下していることから効果的に成果へつなげられない可能性が高まってしまいます。
テレアポ(アウトバウンド)のメリット
さまざまな営業手法の中でも古くから用いられているにも関わらず、現在もなお人気の根強いテレアポ。もちろん現在も多用されているのは、それなりのメリットが備わっているからです。
ここから、テレアポ(アウトバウンド)のメリットを、前述のBDRとSDRに分けてそれぞれ紹介しますので、チェックしてみましょう。手法ごとの特徴を理解することで、実際の運用に役立てられるはずです。
BDRのメリット
まずはBDRの主なメリットを3つ紹介します。アプローチする側から積極的に仕掛ける新規開拓型の営業手法であることは前述しましたが、具体的にはどのようなメリットがあるのかを詳細に解説します。
アプローチ対象をターゲティングできる
BDRは、主体が営業をかける企業側にあり、アプローチ先も自由に選定できる特徴を持っています。そのため、「こうした企業と関係を持ちたい」「こうした企業は多くの収益に期待できる」など、自社が希望する条件にマッチする企業のみを選定してアプローチすることも可能です。
そもそも商材によってはニーズを持つ業種や規模が限定されるケースも多いため、無駄なアプローチを省く上でも「自らアプローチ先を選べる」というのは大きなメリットだといえるでしょう。
また、BDRなら普段関わりの少ない企業との接点や関わりを作ることも可能ですから、営業戦略を自社が主導する形で実現したい場合におすすめです。
休眠ユーザーや未契約部門へアプローチできる
BDRが用いられるのは、過去に接点のない顧客へのアプローチだけではありません。過去に接点はあったものの一定期間自社サービスを利用していない休眠顧客、企業自体とは取引があるもののまだアプローチの余地がある未契約部門へのアプローチにも適しています。
休眠顧客の場合、利用を再開してもらうには「ただ待つ」か「こちらから改めてアプローチ」するかの二択ですが、BDRによって能動的にアプローチすれば、再利用の可能性を高められるでしょう。
また、未契約部門に対してはすでに取引のある部署からヒアリング、紹介などをしてもらった上でアプローチすれば、より精度を高めやすくなります。
ユーザーのニーズを直接聞くことができる
顧客と会話しながらアプローチできるため、相手の課題や悩み、ニーズといった生の情報を一時情報として取得できます。ニーズや課題は分析によって洗い出すことも可能ですが、直接聞き出せるのが最も確実なため大きな価値があります。
SDRのメリット
ここからは、SDRの主な3つのメリットを紹介します。メリットからSDRの特徴や強みを把握し、BDRと比較しながら「どんなシチュエーションに適しているのか」を理解して運用に役立てましょう。
課題が顕在化しているため商談化率が高い
SDRはBDRと違い、営業活動の起点が顧客側にあります。まずは顧客が自ら能動的に資料請求、問い合わせなどを行い、そうしたアクションを起こしたユーザーに対してアプローチを行う形です。
場合によっては、展示会やセミナーの参加者がターゲットとなりますが、少なくとも「ファーストコンタクトがテレアポではない」という点がBDRとの決定的な違いです。SDRの場合、電話でのアプローチ前に顧客と何らかの接点を持っており、また多くの場合において顧客が興味関心を抱いているケースが多いため、課題やニーズが顕在化しているユーザーが大半を占めます。
結果的に顕在化した課題やニーズに合わせてテレアポでアプローチすることにより、商談化しやすいメリットがあります。
保有していないリストへのアプローチができる
BDRは保有している顧客リストの中から、自社の商材の性質や希望する条件に合わせてアプローチを行う対象者を選定します。しかしながらこの方法の場合、アプローチ先を選べる反面、自社で保有していないリストへはアプローチできません。
一方、SDRでは自社でリストを保有していない顧客であっても、問い合わせや資料請求といった相手先からのアクションによりアプローチが可能となります。第一段階の仕掛けとして、リストが不要な広告などで不特定多数に訴求を行うことは可能ですから、仕掛けに興味を持ってもらうことができればリストの有無に関係なく、アプローチにつなげられます。
ユーザーのニーズを直接聞くことができる
BDRと同様に、顧客のニーズや課題を顧客自身の口から直接聞くことができる点は大きなメリットです。マーケティングにはテレアポ以外にもさまざまな手法が存在していますが、例えばWeb広告の場合、検索キーワードの内容やWeb上の履歴などをもとに分析を行い、顧客のニーズや課題を洗い出します。
しかしながら、あくまで間接的な材料をもとにした分析であるため、分析結果が100%正確であるとは限りません。一方、電話であればユーザーと直接会話しながらニーズや課題を掘り起こしていくことが可能なため、信頼性の高い1次情報に触れられるという電話ならではのメリットがあります。
テレアポ(アウトバウンド)のデメリット
BDR、SDRにはそれぞれ異なるメリットが存在していますが、同様にデメリットも複数存在しています。もちろんデメリットがあるからNGというわけではありませんが、BDRとSDRの特徴を正しく理解するには、メリット・デメリットの両方を把握し、「何ができて、どのような場面で役立つのか」を整理する必要があります。ここから、それぞれの主なデメリットを解説しますので、違いを比較しながらチェックしてみましょう。
BDRのデメリット
まずは新規開拓型に分類されるBDRのデメリットを3つ紹介します。大切なのはメリット・デメリットのバランスですから、前述のメリットと合わせて確認しながら自社で運用する際に役立ててください。
SDRと比べて商談化率が低い
BDRは営業をかける側の企業が自発的にアプローチするタイプの手法であるため、反響型のSDRより商談化率が低くなる傾向にあります。特に休眠ユーザーや未契約部門など、これまでに接点のある顧客以外にアプローチする場合、過去の接点がないことから顧客にどの程度ニーズが存在しているのか分からない状態でテレアポを実施する流れとなります。
もちろん中には一定の割合でニーズを持ち合わせている顧客は存在しますが、ニーズが存在しない顧客の割合も大きいため必然的に商談化率はSDRより低くなってしまうのです。商談数を確保するには、リストの質やトークスキルのアップだけではなく、根本的なコール数を増やすための工夫などが求められます。
アプローチまでに時間が掛かる
新規開拓型のBDRでは、テレアポを実施する前の準備が最終的な成果に大きな影響を及ぼします。SDRと比べて商談化率が低いことを踏まえると、一定のコール数を達成することがカギを握りますが、そのためには大量のリストを用意しなければいけません。
また、連絡先だけが記録されたリストよりも、ターゲットの業種、規模、決裁者・担当者など顧客情報が多いほど、情報に合わせて柔軟に対応しやすくなります。しかしながら、これらリスト作りに欠かせない情報収集、リスト管理業務などには入念な準備が必要となるため、立案から実施まで時間がかかる点はデメリットだといえるでしょう。
リストが有限
SDRでアプローチするリストは自社で用意する必要があります。とはいえ、アプローチ可能な企業の情報をすべてそろえるには途方もない時間がかかりますので、ある程度リスト収集が終わった段階でSDRを実施するのが基本です。もちろんテレアポを実施すれば、アプローチ済みの企業はどんどん少なくなっていきますので、テレアポと並行してリスト収集も継続していく必要があります。
加えて、ターゲット先の担当者が変更された、連絡先や所在地が変わった、新事業を始めたなど、変化があった際には都度リスト更新を行う必要があります。リストは自然に増加・更新されるものではありませんので、常にリスト収集や管理が必要な点はあらかじめ留意しておきましょう。
SDRのデメリット
続いては、SDRの主な2つのデメリットを紹介します。反響型であるSDRはBDRより商談化率が高く、保有していないリストへのアプローチも可能な手法ですが弱点も存在していますので、メリットと合わせてチェックしてみましょう。
マーケティング施策が機能していなければ数が少量
SDRは反響型であるとお伝えしましたが、これは裏を返せば、アプローチを行うには資料請求や問い合わせといったユーザー自身からの能動的なアクションを待つ必要があることを意味します。いくらBDRより商談化率が高いとはいえ、発端となるユーザーのアクションが少なすぎては十分な成果を得るのは難しくなってしまいます。
そのため、ユーザーからのアクションを促すマーケティング部門と連携しながら、より多くの反響を得られる施策を実施する必要があります。広告やWebサイトなどの受動的な施策だけでなく、展示会、セミナーといった交流型のイベントを組み合わせて、顧客との接点を増やすのもひとつの手でしょう。
ターゲットとしていないユーザーの対処も必要
SDRは反響型であるだけに、顧客を自社で自由に選定できません。あくまで何らかのアクションを起こしたユーザーに対してアプローチするという考え方に基づいているからです。問い合わせ、資料請求など、アクションの形自体は同じであっても、興味関心の度合いは顧客によってばらつきがあるもの。
そのため、獲得したリードの質にはバラつきがあることを念頭に置く必要があります。場合によっては想定しているターゲットとは異なるユーザーが流入してくる可能性もあるため、すべての顧客に対して画一的に対処するのではなく、ある程度ターゲティングした上で対応内容を使い分けると良いでしょう。
テレアポ(アウトバウンド)の流れ
テレアポ(アウトバウンド)を検討しているものの、実際にどのような準備が必要なのか、具体的にどのように進めるべきなのかが分からないという方もいらっしゃるでしょう。そこでここからは、テレアポ(アウトバウンド)の流れを以下3つのプロセスに分けて解説します。
1.事前準備
2.架電
3.振り返り
各プロセスの具体的な内容やポイントを分かりやすく解説しますので、参考にしてください。
事前準備
テレアポの準備として欠かせないのが「架電先リストの作成」です。リストを作成するにはまず、自社商材のターゲットとなりうる業種や環境を明確化し、合致する企業情報を収集・整理する必要があります。その後、整理したリストを見ながら架電していく流れとなりますので、PCで表示する、印刷するなど、オペレーターが活用したい形に整えましょう。
PCで表示する形にすれば印刷コストを抑えられますし、会話履歴の記録、情報更新なども容易ですので、できればデジタルな形でリスト出力するのがおすすめです。また、トークの質を維持し、営業品質を高めるために、台本となるトークスクリプトも用意しましょう。
架電
リストとトークスクリプトを用意した後は、いよいよ架電です。テレアポでは「〇時間行う」「〇件架電する」など、テレアポを実施する時間や件数を事前に設定するのが一般的です。こうした明確な数値を設定することで架電効率を高めやすくなり、オペレーターのモチベーションアップにもつながります。
また、架電中は単に顧客と会話するだけでなく、通話内容を記録する作業も忘れないようにしましょう。1回の架電でアポが取れない場合でも記録を残しておけば次回のアプローチに役立ちますし、アポ獲得後の商談においても通話中に得た情報は欠かせませんので、オペレーターが情報を記録・共有しやすい環境を用意しておきましょう。
振り返り
架電後は、他のマーケティングと同様に結果を振り返ることも忘れないようにしましょう。PDCAサイクル(計画、実行、評価、改善を繰り返すサイクル)を継続的に回して、テレアポの質を高めていくために、振り返りは欠かせないプロセスです。
・コール数
・架電時間
・商談化率
・獲得商談数
・コンタクト数(相手が電話に出た数)
上記の情報を分析することでオペレーターそれぞれの架電効率や商談獲得率などを洗い出します。さらに、洗い出したデータを全体的な平均と比較することで、オペレーター一人ひとりの優れている点や課題を明確にしましょう。また、通話の中で得た記録を分析して顧客の課題やニーズを整理しておけば、次回以降のテレアポに活かしやすくなります。
テレアポ(アウトバウンド)のコツ
テレアポ(アウトバウンド)は実施する企業によって効率や成果が大きく異なります。もちろんそれは偶然ではなく、効果的なテレアポを実現している企業は重要なポイントを押さえられているからにほかなりません。
そこでここからは、テレアポを実施する上で押さえておくべき3つのコツを紹介します。バランスよく取り入れることで、最終的な成果や電話効率アップに役立ちますのでぜひ参考にしてください。
トークスクリプトの磨き込み
テレアポではもはや必須のツールといえるトークスクリプトですが、一度完成させたトークスクリプトはそのまま使い続けるのではなく、磨き込みことで質を高められます。実践してみるとよく分かりますが、最初に作ったトークスクリプトが最高の結果を招くことはほとんどありません。
むしろ「用意していたフレーズのリアクションが薄い」「想定していたリアクションと実際のリアクションが異なる」「切り返しがうまくできない」など、顧客と会話する中でトークスクリプトの課題が浮かび上がってくるものです。
したがって、トークスクリプトは常に改善・改良を加えて磨き込んでいくことにより、オペレーター全体のパフォーマンスが底上げされ、効果を高めやすくなります。
Q&Aの準備
テレアポは営業手法のひとつではあるものの、プレゼンではありません。あくまで相手との「対話」が大切であり、一方的にしゃべるような展開になると相手にとってはストレスとなってしまいます。
そこで心がけたいのが、こまめに質問を入れ込み、相手と対話する流れを作る方法です。質問を交えることで一方的にこちら側だけが話す展開を避けられるとともに、相手の悩みやニーズを掘り起こせるため、効果的なアプローチにも役立ちます。この際、事前に用意した質問、よくある質問に対するQ&Aを用意しておけば、オペレーターごとの個人的なスキルに頼ることなく適切に回答しやすくなるでしょう。
データの蓄積/活用
テレアポを実施する際には、以下のようなさまざまなデータを収集・管理できる環境を整えておきましょう。
・コール数
・1件あたりの通話時間
・アポ数
・アポ率
・通話内容(録音)
・電話で聞き出した顧客情報
こうした情報を蓄積して活用すれば、現状の良い点・悪い点を洗い出しやすくなります。例えば架電効率が悪いなら顧客管理システムを導入する、アポ率が低いならトークスクリプトを修正するなど、蓄積したデータから導き出された分析結果に基づき、都度改善と検証を繰り返していくのです。
こうした積み重ねがテレアポの効果を高めていく秘訣だと考えるようにしましょう。
テレアポ(アウトバウンド)を行う方法
テレアポ(アウトバウンド)を実施するにあたって多くの方が疑問に抱くのは「自社でやるべきか?外注すべきか?」「誰がやるか?」といった点です。実際、テレアポを導入する企業によって運用方法はさまざまですから、どの方法が最適なのか悩むのも無理はありません。
そこでここからは、テレアポの主な3つの運用方法を順に解説しますので、それぞれの特徴を把握しながら自社での運用に役立ててください。
自社の営業担当(フィールドセールス)で行う
まずは自社の営業担当(フィールドセールス)が自らテレアポを実施する方法です。自分でアポを獲得した顧客に対して自らがそのまま商談まで対応する形となります。メリットとしては、テレアポ時に顧客から得た情報や印象をそのまま商談に活かせるという点でしょう。
もちろん通話内容を記録して引き継ぐことはできますが、顧客の温度感や微妙な空気感まで正確に引き継ぐのは至難の業であるため、1次情報を自分の耳で聞いた本人がそのままアプローチした方が活かしやすくなるのは確かです。
一方でこのパターンの場合は、テレアポと商談を両立する必要があるため営業活動全体の効率は悪くなってしまいます。
自社のインサイドセールスで行う
自社のインサイドセールスチームが専属でテレアポに取り組む方法です。テレアポを内製化している場合は最も一般的な方法であり、テレアポに専念できるため架電効率を高めやすいのが大きなメリットです。
何といっても専門チームがテレアポにあたる場合、他のさまざまな業務と兼用する必要がありません。営業担当者がテレアポと商談を兼用する場合、テレアポのスキルアップに加えて、商談のスキルアップ、対人コミュニケーションの強化などさまざまな点に気を配らなければいけません。
一方、専門のインサイドセールスチームがテレアポに対応すれば、他の業務に力を割く必要は少ないですし、テレアポのスキルだけに専念できるため精度も高めやすくなります。
営業代行会社に外注する
テレアポを取り入れる企業の中には、営業代行会社に外注しているところも多く存在しています。テレアポを外注する主なメリットを以下にまとめますのでご覧ください。
・テレアポにかかる社内工数をカットできる
・コア業務に専念できる
・自社でテレアポ関連の人材を採用する必要がない
・専門的なノウハウ、経験が豊富なプロが対応してくれる
・テレアポに必要な設備やツールを導入する必要がある
・立ち上げまで時間がかからない
これらの要素を自社運用でクリアするには、相当な人材、コスト、時間、手間が求められるでしょう。
そのため、割ける工数が少ない場合やノウハウがない場合、設備の導入が必要な場合などには、外注するというのも有効な選択肢のひとつです。
テレアポ(アウトバウンド)の注意点
テレアポ(アウトバウンド)は適切に実施すれば、貴重な商談機会の創出を効率よくもたらしてくれますが、一方で以下のような「失敗のリスクを高める注意点」もいくつか存在しています。
・架電リストの重複
・架電効率の把握
・他アポイント獲得チャネルとの比較
ここからは上記の注意点を分かりやすく解説しますので、「なぜ注意すべきなのか?」を考えながらチェックしてみてください。
架電リストの重複
テレアポ(アウトバウンド)実施時にまず注意すべきなのが、架電リストの重複です。テレアポを複数名体制で実施するケースは多いですが、リストの管理・運用体制が整っていないと同じ顧客に対して立て続けに架電してしまうようなリスクが高まります。
顧客からすれば、「さっきかかってきたばかりなのに」「しつこい」などストレスを感じる原因となるでしょう。また、同一の担当者が同じ顧客に度々架電してしまうリスクも同様に注意が必要です。こうしたリスクを回避するには、テレアポに対応した顧客管理システムやリスト管理システムを導入し、重複が発生しない環境を事前に構築しておくことが大切です。
架電効率の把握
そもそもテレアポの商談化率は平均で2%前後、上級者でも5%程度だといわれています。つまり、平均すると50件架電して1件商談化に至る割合ですから、ある程度の架電数をこなさなければ商談数自体も増えません。
しかしながら、架電効率は担当者によってばらつきが出るものですから、組織として架電効率をアップさせる工夫を行うことが大切です。
・トークスクリプトを改善する
・操作性に優れた顧客管理システムを導入する
・架電効率の悪い担当者の通話内容をチェックして、問題点を改善する
・テレアポ時の業務フローを見直す
などなど、方法はさまざまですが、架電効率が良い担当者とそうでない担当者の違いを分析した上で、実際の対策に落とし込んでいくと良いでしょう。
他アポイント獲得チャネルとの比較
テレアポを始めたからといって、とことんテレアポにこだわり続ける必要はありません。そもそもテレアポはアポイント獲得チャネルのひとつであり、その他にもリード獲得が可能な方法は数多く存在しています。
そのため商材や環境、社内体制によっては、テレアポにかかっている費用を他の施策や業務に振り替えたほうが効率よくリード獲得を達成できる可能性も十分に考えられます。あくまで大切なのは費用対効果ですから、まずはテレアポにかかっているコストを把握した上で「商談化や商談成立にかかったコスト」を算出しましょう。
その上で他の施策と費用対効果を比較しながら、テレアポを他の施策に変える、他の施策と組み合わせて多角的に展開するなど、効率の良いスタイルを模索していくと良いでしょう。
テレアポ(アウトバウンド)の代替手段にはビジネスマッチング
テレアポ(アウトバウンド)は運用の仕方次第で効率的なリード獲得につながりますが、思うような成果をあげられていない企業が多いのも事実です。
実際、テレアポで十分な成果を出すには、人材の確保、社内体制の整備、各種設備やツールの導入、リスト収集・管理、トークスクリプトの作成など、クリアすべき要素がいくつも存在しています。そのため、テレアポに難しさを感じるのであれば、代替手段としてビジネスマッチングサービス「アイミツCLOUD」を検討してみてはいかがでしょうか。
アイミツCLOUDは「仕事を発注したい人・受注したい人」を結ぶ会員制ビジネスマッチングサービスであり、BtoB領域において100以上のジャンルに対応しています。受注者は自社の情報を掲載することで発注者からの見積もり・発注依頼を受けられるため、専門的なノウハウや多額のコストをかけずにリード獲得が狙えます。
まとめ

今回お伝えしたとおり、テレアポは「見込み客への接点創出」という非常に重要な機会をもたらす上で効果的な営業手法であり、さまざまな業種・ジャンルで未だ根強い人気を保っています。しかしながら、テレアポで効率的なリード獲得を達成するには、架電効率を高めるために人材、設備、ノウハウなど複数の要因をそろえる必要があります。これらさまざまな要因をクリアするのが難しい場合、テレアポ以外の手法を検討してみるのも良いでしょう。
アイミツCLOUDなら、専門的なノウハウやリソースが不足している企業でも、発注者とマッチングする機会を得られますので、まずはお気軽にお問い合わせください。